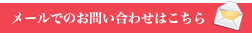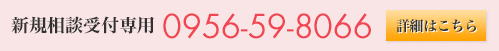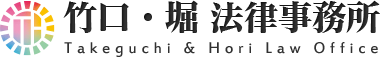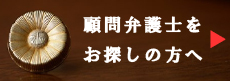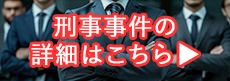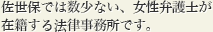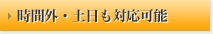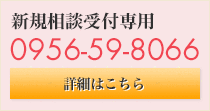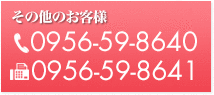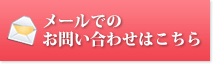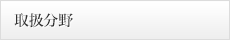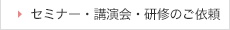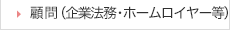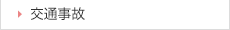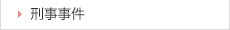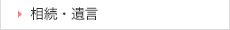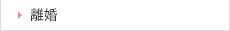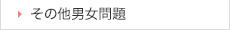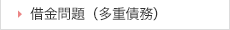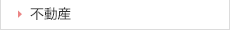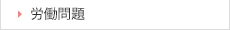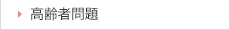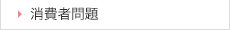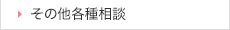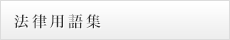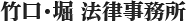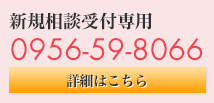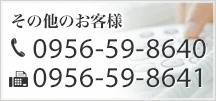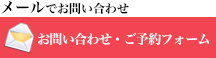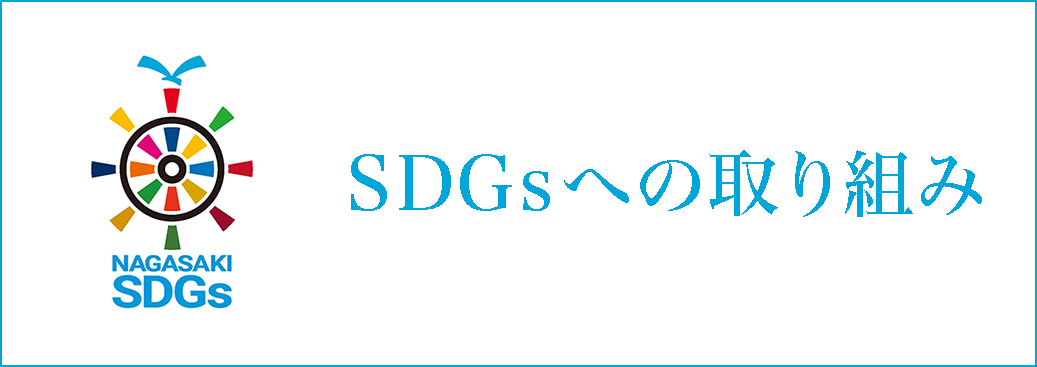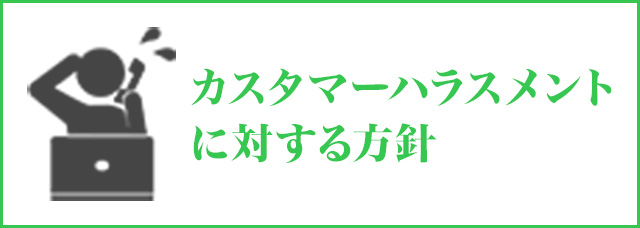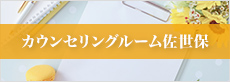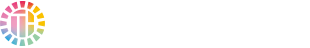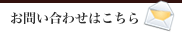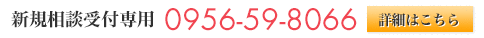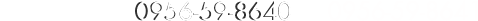カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2019年11月 (3)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2015年9月 (4)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (3)
- 2014年10月 (2)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (7)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (6)
- 2013年12月 (2)
最近のエントリー
HOME > トピックス > アーカイブ > 2025年10月アーカイブ
トピックス 2025年10月アーカイブ
改正育児・介護休業法(第2弾・2025年10月1日から施行)
今回ご紹介しますのは、2025年(令和7年)10月1日より、改正育児・介護休業法の第2弾についてご紹介します。
改正育児・介護休業法のポイント(2025年4月・10月施行)
改正育児・介護休業法(育介法)は段階的に施行されており、主な改正の第1弾が2025年4月1日、
第2弾が2025年10月1日から施行されます。本改正の最大の目的は「育児期の男女が共に希望に応じて
キャリア形成と両立できる仕組みを構築する」こと、すなわち男性の育児参加を念頭に置いた支援の拡充です。
1・「子の看護等休暇」の拡充
・名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。
・取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園・入学式、卒園式」が追加され、
対象となる子の年齢は小学校3年生修了までに拡大されました。
※1年あたりの取得日数(現行:1年に5日、子が2人以上なら10日)は変更されていません。
2・所定外労働の制限(いわゆる残業免除)の拡大
これまで請求対象だった「3歳未満の子を養育する労働者」から、
改正により小学校就学前の子を養育する労働者まで請求できる範囲が拡大されます(請求に応じて所定外労働を免除できる制度)。
3・短時間勤務が困難な場合の代替措置に「テレワーク」を追加(育児のためのテレワーク導入)
3歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務制度の適用が困難な場合、
従来の代替措置メニューにテレワークが追加されました。
これに関連して、事業主には3歳未満の子を持つ者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務
とされています(義務化ではなく努力義務である点にご注意ください)。
1・「3歳〜小学校就学前」の子を持つ労働者に対する事業主の義務化
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、
以下の5つの措置(選択肢)のうち2つ以上を講じる義務があります。労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
・テレワーク等(月10日以上利用できるもの)
・保育施設の設置・運営等(ベビーシッター手配や費用負担等を含む)
・養育両立支援休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可)
・短時間勤務制度(原則として1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む)
2・個別の周知・意向確認の義務化
事業主は、対象となる労働者に対して、施策の周知および個別の意向確認(面談等)を行う義務があります。
導入にあたっては、過半数労働組合等からの意見聴取も必要です。
・日付・施行の段階:原文は「第1弾が4月、第2弾が10月」とありましたが、
正式には2025年4月1日(第1弾)と2025年10月1日(第2弾)です。施行対象の項目ごとに異なるため、記事では日付を明示しました。
・子の看護等休暇:名称変更、取得事由の追加(感染症による学級閉鎖等・入園・入学・卒園式等)、
対象年齢が小学校3年生修了までに拡大された点を明確化しました。取得日数自体は変わっていません。
・残業免除(所定外労働の制限):対象範囲は「3歳未満」から小学校就学前へ拡大、
という点を修正(「小学校3年生修了」ではない点に注意)。(※子の看護等休暇とは別の規定で、対象年齢に差があります。要注意。)
・テレワークの位置づけ:短時間勤務制度が困難な場合の代替措置メニューにテレワークが追加されたこと、
および3歳未満の子を持つ労働者に対してのテレワーク導入は事業主の努力義務であることを明記しました(努力義務と義務化の違いに留意)。
・10月施行の「5つの選択肢」:各選択肢(テレワークは月10日以上、休暇は年10日以上、
短時間勤務は原則1日6時間等)について、制度上の目安を明確化しました。
出典(法的根拠/参照資料)
・厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正ポイント」ページ(施行日・主な改正点の一覧)。
・厚生労働省「令和6年改正 育児・介護休業法に関する Q&A」(詳細な運用Q&A)。
・厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(代替措置メニュー等の図解)。
今回の改正は、単なる制度変更にとどまらず、「子育てを社会全体で支える仕組み」へと一歩進んだものといえます。
特に男性の育児参加を後押しする点は大きな特徴であり、当事務所においても、
勤務時間を1時間繰り上げて退社したり、残業を行わない勤務体制を徹底したりするなど、実際に取り組んでいる男性職員がいます。
こうした取り組みは、今後の企業文化や働き方の見直しにも大きな影響を与えていくことでしょう。
これから先、企業文化や働き方の見直しにも大きな影響を与えるでしょう。
一方で、制度を整備するだけでは十分ではなく、実際に職場で利用しやすい環境をどう作るかが課題となります。
法律事務所として私たちが感じるのは、法改正を契機に「制度を知ること」「働き方を話し合うこと」が重要だということです。
企業にとっても労働者にとっても、これを前向きに活用する姿勢が、安心して働ける社会づくりにつながるのではないでしょうか。
---------------------------------------
竹口・堀法律事務所
改正育児・介護休業法のポイント(2025年4月・10月施行)
改正育児・介護休業法(育介法)は段階的に施行されており、主な改正の第1弾が2025年4月1日、
第2弾が2025年10月1日から施行されます。本改正の最大の目的は「育児期の男女が共に希望に応じて
キャリア形成と両立できる仕組みを構築する」こと、すなわち男性の育児参加を念頭に置いた支援の拡充です。

1・「子の看護等休暇」の拡充
・名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。
・取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園・入学式、卒園式」が追加され、
対象となる子の年齢は小学校3年生修了までに拡大されました。
※1年あたりの取得日数(現行:1年に5日、子が2人以上なら10日)は変更されていません。
2・所定外労働の制限(いわゆる残業免除)の拡大
これまで請求対象だった「3歳未満の子を養育する労働者」から、
改正により小学校就学前の子を養育する労働者まで請求できる範囲が拡大されます(請求に応じて所定外労働を免除できる制度)。
3・短時間勤務が困難な場合の代替措置に「テレワーク」を追加(育児のためのテレワーク導入)
3歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務制度の適用が困難な場合、
従来の代替措置メニューにテレワークが追加されました。
これに関連して、事業主には3歳未満の子を持つ者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務
とされています(義務化ではなく努力義務である点にご注意ください)。

1・「3歳〜小学校就学前」の子を持つ労働者に対する事業主の義務化
事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、
以下の5つの措置(選択肢)のうち2つ以上を講じる義務があります。労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤など)
・テレワーク等(月10日以上利用できるもの)
・保育施設の設置・運営等(ベビーシッター手配や費用負担等を含む)
・養育両立支援休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可)
・短時間勤務制度(原則として1日の所定労働時間を6時間とする措置を含む)
2・個別の周知・意向確認の義務化
事業主は、対象となる労働者に対して、施策の周知および個別の意向確認(面談等)を行う義務があります。
導入にあたっては、過半数労働組合等からの意見聴取も必要です。
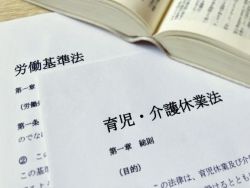
・日付・施行の段階:原文は「第1弾が4月、第2弾が10月」とありましたが、
正式には2025年4月1日(第1弾)と2025年10月1日(第2弾)です。施行対象の項目ごとに異なるため、記事では日付を明示しました。
・子の看護等休暇:名称変更、取得事由の追加(感染症による学級閉鎖等・入園・入学・卒園式等)、
対象年齢が小学校3年生修了までに拡大された点を明確化しました。取得日数自体は変わっていません。
・残業免除(所定外労働の制限):対象範囲は「3歳未満」から小学校就学前へ拡大、
という点を修正(「小学校3年生修了」ではない点に注意)。(※子の看護等休暇とは別の規定で、対象年齢に差があります。要注意。)
・テレワークの位置づけ:短時間勤務制度が困難な場合の代替措置メニューにテレワークが追加されたこと、
および3歳未満の子を持つ労働者に対してのテレワーク導入は事業主の努力義務であることを明記しました(努力義務と義務化の違いに留意)。
・10月施行の「5つの選択肢」:各選択肢(テレワークは月10日以上、休暇は年10日以上、
短時間勤務は原則1日6時間等)について、制度上の目安を明確化しました。
出典(法的根拠/参照資料)
・厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正ポイント」ページ(施行日・主な改正点の一覧)。
・厚生労働省「令和6年改正 育児・介護休業法に関する Q&A」(詳細な運用Q&A)。
・厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(代替措置メニュー等の図解)。
今回の改正は、単なる制度変更にとどまらず、「子育てを社会全体で支える仕組み」へと一歩進んだものといえます。
特に男性の育児参加を後押しする点は大きな特徴であり、当事務所においても、
勤務時間を1時間繰り上げて退社したり、残業を行わない勤務体制を徹底したりするなど、実際に取り組んでいる男性職員がいます。
こうした取り組みは、今後の企業文化や働き方の見直しにも大きな影響を与えていくことでしょう。
これから先、企業文化や働き方の見直しにも大きな影響を与えるでしょう。
一方で、制度を整備するだけでは十分ではなく、実際に職場で利用しやすい環境をどう作るかが課題となります。
法律事務所として私たちが感じるのは、法改正を契機に「制度を知ること」「働き方を話し合うこと」が重要だということです。
企業にとっても労働者にとっても、これを前向きに活用する姿勢が、安心して働ける社会づくりにつながるのではないでしょうか。
---------------------------------------
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2025年10月 1日 18:11





1