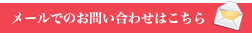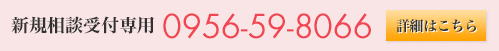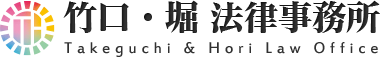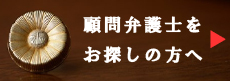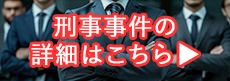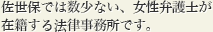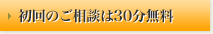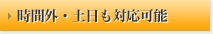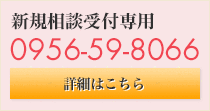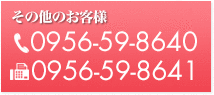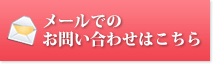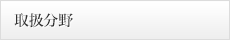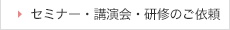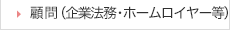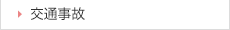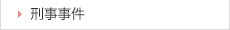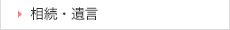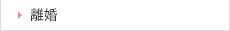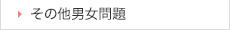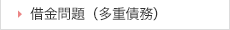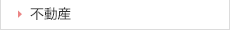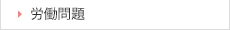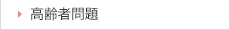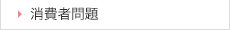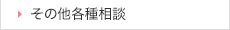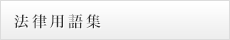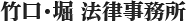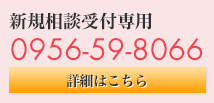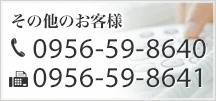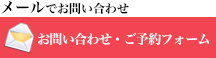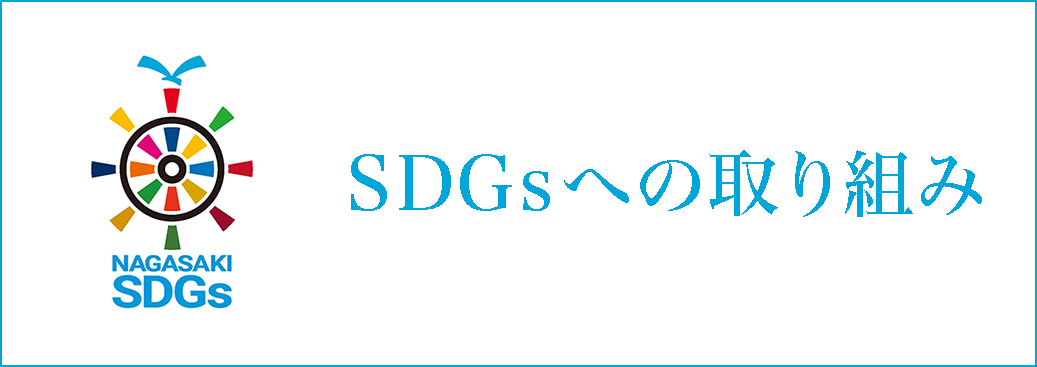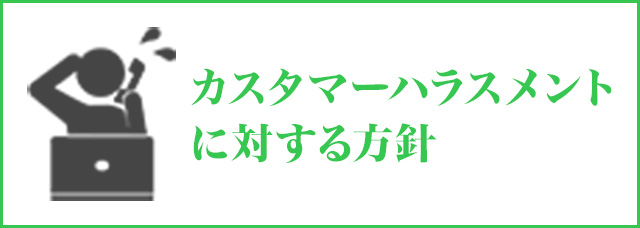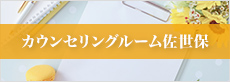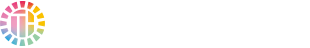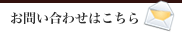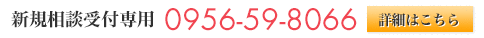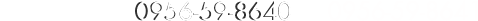カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年10月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2019年11月 (3)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年7月 (1)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2015年9月 (4)
- 2015年6月 (1)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (4)
- 2015年3月 (1)
- 2015年1月 (3)
- 2014年10月 (2)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (6)
- 2014年4月 (7)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (6)
- 2013年12月 (2)
最近のエントリー
HOME > トピックス
トピックス
地方自治体(行政)と弁護士の連携
日弁連でも,各地方自治体と各弁護士会との連携について,様々な取り組みが紹介されています。
例として,以下では,北海道の取り組みをご紹介します。
第1に,旭川では,弁護士が自治体の「地域司法対策委員」となって活動しているようです。第2に,釧路では,無料法律相談会や,小中学校での出前授業,地域包括支援センターとの連携を行っているようです。第3に,函館では,各分野における函館市その他関係団体等当との連携やネットワークづくり等を行っているそうです。第4に,札幌では,弁護士不在自治体における頻回相談事業,札幌市の公金債権管理回収業務に関するメール相談事業等を行っているそうです。
このような取組は,全国各地の弁護士会や自治体でなされています。弁護士が,任期付職員として地方自治体内部で活躍する例も少なくありません。
長崎県弁護士会(佐世保支部も含む)でも,長崎市や佐世保市などの県内の自治体と連携して,様々な取り組みを行っています。
(竹口・堀法律事務所)
2015年1月21日 23:34





弁護士保険の新規協定締結(日弁連)
これまで、日弁連LACが進めてきた弁護士紹介制度は、自動車保険等の特約として販売されるものだけであり、交通事故に起因する損害賠償請求事案等に範囲が限られてきました。
しかしながら、今回の新規協定締結により、交通事故等の損害賠償請求事案に限らず、一般の民事紛争にまで補償範囲が拡大されることになります。
したがって、弁護士保険の制度が、今後は、より利用しやすくなるといえそうです。
(竹口・堀法律事務所)
2015年1月19日 20:16





ストーカーの発生件数等
警視庁によると,ストーカー行為等の相談受理状況は,平成24年度で1437件となっており,前年度と比較して44.7%増加しています。
被害者の性別をみると,平成24年度においては,女性が85.7%,男性が14.3%であり,過去4年間も同様の傾向にあります。
ストーカーの行為態様としては,①面会・交際等の要求が最も多く,次いで,②つきまとい等,以下,③無言・連続電話等,④粗野乱暴な言動,⑤監視行為,⑥性的羞恥心の侵害,⑦名誉の侵害,⑧汚物送付等の順となっています。
警察による援助の実施状況については,①その他被害防止のための適切な援助が最も多く,次いで,②被害防止措置の教示,以下,③被害防止・交渉に必要な事項の連絡,④被害防止交渉に関する助言,⑤被害防止に資する物品の教示・貸出,⑥行為者の氏名及び連絡先の教示,⑦被害防止交渉の警察施設の利用,⑧被害防止活動を行う民間組織の紹介及び警告等を実施した旨の書面の交付の順となっています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月16日 19:26





佐世保・長崎におけるDVの相談件数等
このうち,DV相談対応件数は合計1345件であり,女性相談等対応件数全体の64.3%を占めています。
なお,一時保護状況については,一時保護を必要とする女性は101人,その同伴児童等は82人で,そのうちDVを主訴とするものは70人となっています。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月16日 19:23





長崎・九州における企業の破産(倒産)状況
近年の全国的な統計をみると、全国的に、企業の倒産(破産)は減少傾向にあります。
企業の破産(倒産)が減少している理由については、様々な理由があると思いますが、大きな理由の1つとして、「中小企業金融円滑化法」の存在が挙げられます。
中小企業金融円滑化法は、中小企業を救済するための法律で、同法により、中小企業は、返済がしやすいような融資条件の変更をしてもらったり、追加融資を受けることが、行いやすくなりました。
これにより、数多くの中小企業が、倒産(破産)を免れることができたのではないかと言われています。
もっとも、中小企業円滑化法は平成25年3月に終了することとなったため、専門家の間では、平成25年3月以降は中小企業の破産(倒産)が増加するのではないかと言われていました。
しかしながら、平成25年度(2013年度)の破産件数(倒産件数)をみると、いまだ中小企業の破産件数(倒産件数)の減少傾向は続いているようです。
九州の企業についても、佐賀県・鹿児島県・沖縄県の中小企業については破産件数(倒産件数)が微増したようですが、その他の長崎県・福岡県・熊本県・大分県・宮崎県は、いずれも破産件数(倒産件数)が減少しており、九州全体でみると、中小企業の破産件数(倒産件数)は減少傾向にあるといえます。
当事務所では、佐世保市・平戸市・長崎市などを中心として、中小企業の支援や破産(倒産)等を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
佐世保・長崎・佐賀の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年7月12日 20:23





刑事事件に関する裁判員制度が始まって5年が経ちました
刑事事件に関する裁判員法が施行されて5年が経過したことを踏まえて、日弁連の会長談話が出されました。
会長によると、裁判員裁判制度自体は安定した運用が定着しているとして評価できるとしつつ、上訴審において裁判員の判断が十分に尊重されていないという問題があることや、検察官の活動と比べて弁護人の活動がわかりにくいこと
などが問題点として指摘されています。
長崎・佐世保においても、テレビや新聞の報道などにより、「裁判員裁判」という制度の大まかな仕組みについてはほとんどの市民の皆様が理解されています。
日頃の業務の中でご相談者の方々から裁判員制度について質問されたり、
日常生活の中で友人や知り合いから裁判員制度についての質問をされることもあります。中には、実際に裁判員の候補者になった人が身近にいるという方もいました。
特に長崎市では、最近も重大事件が発生して裁判員裁判が開かれましたから、市民の皆様にとって重大な関心事となっているようです。
もっとも、長崎で裁判員裁判が開かれるのは長崎市(長崎地裁本庁)のみであり、佐世保市(長崎地裁佐世保支部)では裁判員裁判は開かれません。
そのため、佐世保市では、裁判員制度に対する興味・関心は、長崎市内の方々よりもやや薄いかもしれません。
裁判員制度について、全国的には、裁判員となったことにより苦痛を被ったとして国が訴えられたケースが発生したり、裁判員裁判において死刑という判決が下されたにも関わらず上訴審で判決が覆されたケースが発生するなど、裁判
員裁判の運用に関する問題点はまだまだ残されたままです。
なお、前者の問題点については、裁判員に見せる証拠については残酷ではないものや白黒写真に差し替えるなどの工夫がなされているようですが、これによりかえって裁判員が適正な判断ができなくなるのではないかとの意見もあります。
当事務所でも、長崎や福岡の裁判員案件を取り扱っており、被告人側の弁護人となることもあれば被害者側の代理人となることもありますが、今後の裁判員裁判の運用に注目していきたいと思っています。
※裁判員裁判の対象事件は、地方裁判所(長崎地方裁判所、佐賀地方裁判所、福岡地方裁判所など)で行われる刑事裁判(刑事事件、第一審)のうち、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての刑事裁判である。詳しくは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)」で定められており、刑事事件のうち、死刑または無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(裁判員法2条1項1号)や、法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(裁判員法2条1項2号)とされている。
佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年6月 1日 18:20





日弁連がカジノ(カジノ解禁推進法案)に反対する意見書を提出しました
現在、「カジノ解禁推進法案」(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案)が国会に提出され、今国会において審議されているようです。
この法案は、現政府によるいわゆるアベノミクスと呼ばれる経済政策の一環として位置づけられているとも言われています。
具体的には、いわゆるアベノミクスとは、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略のいわゆる「3本の矢」に関する諸政策とともに、経済効果をより高めるため、東京オリンピックの誘致を行うとともに、カジノ解禁を行おうとしていると言われています。
カジノの解禁については、解禁により観光及び地域経済の振興に寄与するとともに財政の改善に資するとの理由で上記法案が提出され、カジノの誘致先としては、長崎県佐世保市のハウステンボスや大阪府が候補地として挙がっています。
佐世保市でも、カジノの誘致に力を入れて取り組んでいるようです。
したがって、長崎県民(佐世保市民)としても、この法案の行方に注目せざるを得ません。
これに対して、今回日弁連が家事の解禁推進法案に反対する意見書を提出した理由は、大まかにいうと以下の6点です。すなわち、
①他国(アメリカや韓国)の例からするとカジノにより経済効果があがるというのはそもそも疑問がある、
②カジノを解禁すると暴力団が関与することが予想されるため暴力団対策上の問題点が生じる、
③他国ではカジノに関するマネーロンダリングが問題となっており、日本でもマネーロンダリング対策上の問題が生じる、
④カジノが解禁されてしまうとギャンブル依存症が拡大してしまう、
⑤カジノの解禁により青少年に悪影響が生じる、
⑥カジノを民間企業の経営に任せると、適切に経営できるのかどうか疑問がある
という6点です。
仮に佐世保へのカジノの誘致が成功した場合、確かに一定の経済効果が見込めるようにも思えますので、佐世保市民としてはカジノの誘致に賛成したい気持ちになるかもしれません。
しかしながら、上記6点のような事柄が十分に議論されないまま上記法案が通ってしまうことには危険を感じますので、慎重な議論がなされることを望むばかりです。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年6月 1日 17:45





弁護士と隣接士業(司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士等)について
弁護士と隣接する士業として,司法書士,行政書士,社会保険労務士,税理士,弁理士などの士業(職業)が存在します。
弁護士資格は,これらの士業の資格を含んでいますので,最近はこれらの士業としての業務を積極的に行う弁護士も増えていますが,基本的には,弁護士は,これらの隣接士業のみなさんと協力して,日頃の業務に取り組んでいます。
しかしながら,近年,弁護士とこれらの士業との関係が問題となるケースも増えています。
2.どうして問題となるのか
(1) はじめに
弁護士法には,「弁護士資格のないものが,報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことを禁止」する条文(72条)があります。
この条文に違反する行為を行った者は,弁護士法違反として,刑事処罰の対象となります。
それにもかかわらず,弁護士でない者が,この条文に違反する行為を行う例が全国的には後を立たないため,現在,日本弁護士連合会や各弁護士会が,調査の上,警告文の発送や裁判所への注意喚起の文書の送付などの対応をしています(日本弁護士連合会における弁護士業務改革委員会による報告)。
具体的に問題となるケースとしては,以下のようなものが報告されています。
(2) 司法書士の場合
例えば,司法書士は,140万円を超える事件の処理を行うことはできませんし,家事事件について代理人となることはできません。しかしながら,司法書士が140万円を超える事件の処理を行ったり,司法書士が家事事件について実質的に代理を行っているケースが報告されています。また,司法書士は「法律事務所」を名乗ることはできないにもかかわらず,司法書士が「法律事務所」を名乗っている例が報告されています。これらのケースでは,当該司法書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(3) 行政書士の場合
また,行政書士は,一般に事件の代理人となる権限がないにもかかわらず,連絡先を当該行政書士とする通知書を作成したり,行政書士が交通事故等の民事事件および家事事件について事実上代理を行っている例,行政書士が「町の法律家」という紛らわしい名刺を配っている例がどが報告されています。これらのケースでは,当該行政書士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(4) 社会保険労務士の場合
社会保険労務士についても,本来は権限がないにもかかわらず,社会保険労務士が残業代請求広告を行ったり,社会保険労務士が労働審判に実質的に関与している例などが報告されています。これらのケースでは,やはり,当該社会保険労務士が,弁護士法72条違反で処罰される可能性があります。
(5) 税理士,弁理士の場合
その他,税理士が遺産分割協議作成したり,弁理士が特許関係契約書を作成するなど,問題のあるケースなどが報告されています。
(6) 宅建業者等の場合
また,士業以外でも,例えば宅建業者は代理人となることができないにもかかわらず,立ち退き交渉などを行ってしまったケースもあります。
3.まとめ
もちろん,大部分の士業の方々は適切に業務を行っていますし,上記2のような問題が起こる背景には,様々な原因があると考えられます。
その原因としては,①一般市民にとって弁護士が敷居が高いため,本来は弁護士に頼まなければならない業務を他の士業に依頼してしまうのではないかということ,②弁護士の職業倫理が厳しいことから,弁護士自体が受任に慎重になりやすいこと,などが一般に挙げられます。
当事務所は,一般市民にとって利用しやすい法律事務所を目指していますし,どんな案件でも全力に取り組んでいますので,お気軽にご相談ください。
また,他の士業への相談案件であっても,弁護士が相談に乗った後,司法書士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,税理士に相談すべき案件であれば信頼できる司法書士に,社会保険労務士に相談すべき案件であれば社会保険労務士に,など,それぞれの信頼できる専門家をご紹介しますので,弁護士に相談すべきかどうか悩む案件であっても,まずは当事務所にご相談ください。
佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年5月19日 23:15





弁護士保険(権利保護保険)制度の利用について
この制度を使えば,同制度を協定を締結している保険会社が弁護士費用を支払ってくれるので,ご依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。
同制度は,交通事故の案件で利用されることが多いですが,交通事故以外の案件でも利用することができます。
弁護士保険の販売件数は,当初の2000年は全国で7397件でしたが,2012年は1978万0575件にものぼりました。
2014年4月現在で,協定保険会社も14社となり,かなり使いやすい制度となりました。14社とは,①あいおいニッセイ同和損害保険会社,②エース損害保険会社,③au損害保険会社,④SBI損害保険会社,⑤株式会社損害保険ジャパン,⑥共栄火災海上保険株式会社,⑦全国共済農業共同組合連合会,⑧全国自動車共済協同組合連合会,⑨ソニー損害保険株式会社,⑩そんぽ24損害保険株式会社,⑪日本興亜損害保険株式会社,⑫富士火災海上保険株式会社,⑬三井住友海上火災保険株式会社,⑭三井ダイレクト損害保険株式会社,です。
これらの保険ないし共済を利用されている方々については,弁護士保険制度(権利保護保険制度)を利用できる可能性がありますので,弁護士に相談・依頼する前にぜひご確認ください。
佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年5月19日 22:27





平戸市消費生活センターが開設されました。
これまで,長崎県内の消費生活センターは,主な市(長崎市,佐世保市,島原市,諫早市,大村市,五島市,雲仙市,南島原市など)には設置されていたものの,平戸市には設置されていませんでした(下記の「参考1:長崎の消費生活センター一覧」参照)。
消費生活センターは,市民のみなさんの消費者生活相談に乗ってくれるところです。
消費生活センターでは,「消費生活専門相談員」という資格を持った方が,みなさんの相談に乗ってくれます。
もちろん,消費者生活相談は,法的な問題を含むことがほとんどですから,本来であれば,法律家である弁護士に相談するのが一番です。
しかしながら,一般市民のみなさんにとって,弁護士(法律事務所)に相談するというのは敷居が高いと思われる方も多いと思います。
また,弁護士に相談した場合の相談料が気になる方もいらっしゃると思います(当事務所は,初回の法律相談は30分無料ですし,2回目以降の法律相談についても,法テラスの要件を充たす場合は無料(相談援助利用可。ただし3回まで。)です)。
そういった方々にとっては,弁護士ではなく消費生活センターに相談してみるというのも,選択肢の1つだと思います。
なぜなら,消費生活センターは公的機関ですので心理的にも相談しやすいでしょうし,公的機関ですので相談料も無料です。
さらに,消費生活センターの相談員さん達は,様々な事例を取り扱っていますので,安心して相談できます。
ちなみに,弁護士も消費生活相談員の方々も,お互い消費者問題を取り扱うという意味では共通しています。
ですから,当事務所の弁護士は,情報交換等のために,様々な機会を通じて長崎県内各地の消費生活相談員のみなさんと一緒に勉強会をしたりしながら,更なる研鑚につとめています。
また,弁護士は,法律の専門家として,各地の消費生活相談センターに出向いて,消費生活相談員の方と一緒にご相談を受けることもあります。
当事務所の弁護士も,定期的に,佐世保市消費生活センターなどに赴いて,法律相談(消費生活相談)を受けています。
なお,長崎県では,上記消費生活センター以外にも,県内の21市町において,消費生活相談窓口があります(下記の「参考2:長崎の消費生活相談窓口一覧」参照)。
<参考1:長崎の消費生活センター一覧>
◆長崎県消費生活センター
◆長崎市消費生活センター
◆佐世保市消費生活センター
◆島原市消費生活センター
◆諫早市消費生活センター
◆大村市消費生活センター
◆五島市消費生活センター
◆雲仙市消費生活センター
◆南島原市消費生活センター
<参考2:長崎の消費生活相談窓口一覧>
◆長崎市:長崎市消費生活センター
◆佐世保市:佐世保市消費生活センター
◆島原市(有明支所):島原市消費生活センター市民生活課
◆諫早市:諫早市消費生活センター
◆大村市:大村市消費生活センター
◆五島市:五島市消費生活センター
◆雲仙市:雲仙市消費生活センター
◆南島原市:南島原市消費生活センター
◆平戸市
・市民課 市民総合相談室
・(生月支所):市民協働課 市民協働班
・(田平支所):市民協働課 市民保健班
・(大島支所):市民協働課 市民協働班
◆松浦市:松浦市消費生活センター
◆対馬市
・観光物産推進本部
・(美津島地域活性化センター):地域支援課
・(豊玉地域活性化センター):地域支援課
・(峰地域活性化センター):地域支援課
・(上県地域活性化センター):地域支援課
・(上対馬地域活性化センター):地域支援課
◆壱岐市
・観光商工課
・(郷ノ浦支所):観光振興課
◆西海市
・西海市消費生活センター
・(西彼総合支所):市民課
・(西海総合支所):市民課
・(大島総合支所):市民課
・(崎戸総合支所):市民課
◆長与町:地域政策課
◆時津町:産業振興課商工労政係
◆東彼杵町:総務課企画係
◆川棚町:総務課行政係
◆波佐見町:商工企画課商工観光係
◆小値賀町:産業振興課商工観光班
◆佐々町:産業経済課商工観光班
◆新上五島町
・総合窓口課
・(若松支所)
・(奈良尾支所)
・(新魚目支所)
・(有川支所)
佐世保・長崎・佐賀・福岡の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年5月14日 20:33