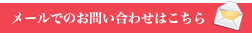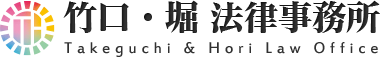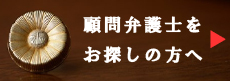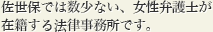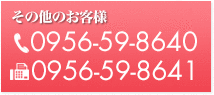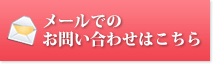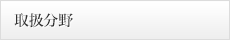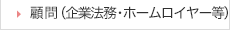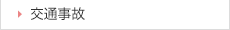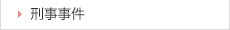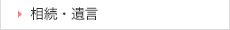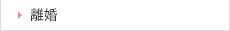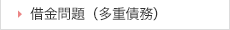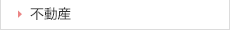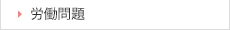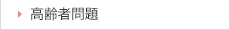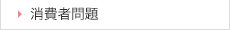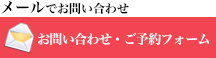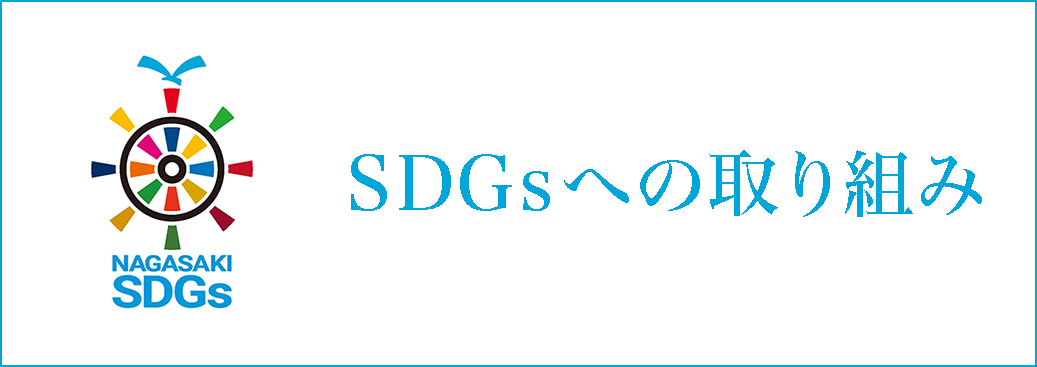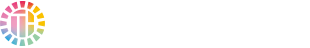HOME > 判例(裁判例)紹介
判例(裁判例)紹介
離婚後の監護費用の請求(H23.3.18判決)
今回は,離婚後の子どもの監護費用(養育費)の請求が,権利濫用にあたり認められないとされた判例(最判平成23年3月18日(平成21年(受)第332号)離婚等請求本訴,同反訴事件)を紹介します。
(事案の概要)
本件は,X(夫)が,Y(妻)に対し,離婚等を請求するなどし,Yが,反訴として,Xに対し,離婚等を請求するとともに,長男,二男及び三男の養育費として,判決確定の日から,長男,二男及び三男がそれぞれ成年に達する日の属する月まで,一人当たり月額20万円の支払いを求める旨の監護費用の分担の申立て等をした事案である。
Xは,監護費用について,二男との間には自然的血縁関係がないことから,監護費用を分担する義務はないと主張した。なお,Xは,本件提訴前,二男との間の親子関係不存在確認の訴え等を提起したが,同訴えについては却下する判決が言い渡され,同判決は確定している。
原審は,Xと二男との間に法律上の親子関係がある以上,Xはその監護費用を分担する義務を負うと判断した。
(最高裁判所の判断)
最高裁判所は,YがXに対し離婚後の二男の監護費用の分担を求めることは,権利の濫用に当たるとした。
理由は以下のとおり。YはXと婚姻関係にあったにもかかわらず,X以外の男性と性的関係を持ち,その結果,次男を出産したが,それから約2か月以内に二男とXとの間に自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず,これをXに告げず,Xがこれを知ったのは二男の出産の7年後のことであったため,Xは,二男につき,民法777条所定の出訴期間内に嫡出否認の訴えを提起することができず,そのことを知った後に提起した親子関係不存在確認の訴えは却下され,もはやXが二男との親子関係を否定する法的手段は残されていない。他方,Xはこれまでに二男の養育・監護のための費用を十分に負担してきており,Xが二男との親子関係を否定することができなくなった上記の経緯に照らせば,Xに離婚後も二男の監護費用を分担させることは,過大な負担を課すものである。YはXとの離婚に伴い,相当多額の財産分与を受けることになるのであり,離婚後の二男の監護費用を専らYに分担させることができないような事情はうかがわれないから,子の福祉にも反しない。
以上の事情を総合考慮すると,YがXに対し離婚後の二男の監護費用の分担を求めることは,監護費用の分担につき判断するに当たっては子の福祉に十分配慮すべきであることを考慮してもなお,権利の濫用に当たるというべきである。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月25日 15:16





葬儀費用の請求(H24.3.29判決)
相続や遺言の案件,成年後見に関する案件などにおいて,葬儀費用を誰が負担すべきかということが問題となることがあります。
そこで,今回は,葬儀費用の負担に関する裁判例(名古屋高判平成24年3月29日(平成23年(ネ)第968号)貸金返還等請求控訴事)についてご説明します。
(事案の概要)
亡Aは,平成21年12月に死亡し,その相続人は,長男Y1及び二男Y2であった。Xは,亡Eの兄弟であったところ,喪主として亡Aの葬儀等を主宰し,通夜,葬儀,火葬及び初七日の法要を行った。
そこで,Xは,葬儀費用は相続財産又は相続人が負担すべきであるなどと主張して,Yらに対して,①Xが支出した葬儀費用について不当利得返還請求をした。
その他にも,Xは,亡Aが締結していた賃貸借契約の解約をし,原状回復費用として10万1588円を支出したとして,Yらに対し,②事務管理に基づく費用償還請求権に基づき,それぞれ5万円余の支払を,③Xが,亡Aの債務を立替払いしたと主張して,Yらに対し,それぞれ8000円余の支払を,④Xが,亡Aに対し,2回にわたって計100万円を貸し付けたとして,金銭消費貸借契約に基づき,Yらに対し,それぞれ50万円の支払を求めた。
原審は,②③を認め,その余の請求を棄却したため,Xは敗訴部分を不服として控訴した。
(裁判所の判断)
本件においては,特に,Xが亡Aの葬儀費用を支出したとして他の相続人らに返還請求を求めた点に対する判断を取り上げたい。
裁判所は,一般論として,葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当であるとした。
そして,本件については,亡Aは予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡Aの相続人であるYらや関係者であるXらの間で,葬儀費用の負担についての合意がない状況において,Xが,亡Aの追悼儀式を手配し,その規模を決め,喪主も務めたのであるから,Xが亡Aの追悼儀式の主宰者であったと認められ,Xが亡Aの追悼儀式の費用を負担すべきものというべきである。他方,亡Aの遺骸,遺骨の埋葬等の行為に要する費用については,亡Aの祭祀を主宰すべき者が負担すべきものであるが,亡Aの祭祀を主宰すべき者については,亡Aにおいてこれを指定していた事実は認められないから,民法897条1項本文により,慣習に従って定められるべきものであるが,亡AにはYらという二人の子があるものの,20年以上も親子の交渉が途絶えていた状況である一方,兄弟であるXらとの間に比較的密な交流があった事情が認められることも考慮すると,亡Aの祭祀を主宰すべき者を亡Aの子であるYら又はそのいずれかとすることが慣習上明白であると断ずることはできず,結局,本件における証拠をもってしては,亡Aの祭祀を主宰すべき者を誰にすべきかに関する慣習は明らかでないというほかない。そうすると,家庭裁判所で,同条2項に従って,亡Aの祭祀承継者が定められない限り,亡Aの遺骸等の埋葬等の行為に要する費用を負担すべき者が定まらないといわざるを得ない。
したがって,XがYらに対し,葬儀費用を請求する法的根拠はないというべきであるとした。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月25日 15:11





「相続させる」遺言の効力(H23.2.22判決)
相続・遺言の案件では,「相続させる」旨が記載された遺言の効力がよく問題となります。そこで,今回は,これに関する判例(最判平成23年2月22日(平成21年(受)第1260号)土地建物共有持分権確認請求事件)について説明します。
(事案の概要)
被相続人Aは,平成5年2月17日,Aの所有に係る財産全部をAの子であるBに相続させる旨を記載した公正証書遺言書を作成した。Bは,その後,平成18年6月21日に死亡し,Aが同年9月23日に死亡した。Aの子であるXは,遺産の全部をAのもう一人の子であるBに相続させる旨のAの遺言は,BがAより先に死亡したことにより効力を生ぜず,XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して,Bの子であるYらに対し,Aが持分を有していた不動産につきXが上記法定相続人に相当する持分等を有することの確認を求めた。
原審は,本件遺言は,BがAより先に死亡したことによって効力を生じないこととなったというべきであるとして,Xの請求を認容したが,これを不服としてYが上告した。
(最高裁判所の判断)
本件の争点は,「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力である。
最高裁場所は,まず,「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情および遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとした。
そのうえで,本件においては,BはAの死亡以前に死亡し,本件遺言書には,Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく,BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上,本件遺言作成時,Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことから,上記特段の事情も認められず,本件遺言はその効力を生じないとした。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月22日 22:26





婚約破棄と慰謝料(H24.3.28判決)
当事務所では,離婚問題以外にも,様々な男女問題を取り扱っております。
離婚問題以外の男女問題として多いのは,婚約破棄や内縁解消に関する問題ですので,今回は,婚約破棄に基づく慰謝料に関する裁判例(岡山地判平成24年3月28日(平成19年(ワ)第2021号))をご紹介します。
(事案の概要)
本件は,原告が,昭和61年に他の男性と婚姻して一男一女を出産し,平成19年7月に参議院議員選挙に当選した被告に対し,平成13年12月に性的関係を持ち,平成16年2月に伊勢神宮に特別参拝して婚約していたのに,参議院議員選挙出馬を控えた平成18年10月,被告から婚約を不当に破棄されたとして,不法行為に基づく損害賠償として慰謝料2800万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。
(裁判所の判断)
本件の争点は①婚約が成立していたといえるか,②婚約を不当に破棄したといえるか等である。
裁判所は,まず一般論として,婚約(婚姻の予約)は,諾成契約であるから,当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約したものであれば足り,必ずしも同棲を伴う必要はなく,また,結納などの特段の方式も不要であるけれども,何ら外形的な事実関係を伴わない場合には,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるというべきであるとした。
その上で,本件において,原告と被告は,遅くとも平成14年3月下旬ころから平成18年10月ころまでの長期にわたり,二人で全国各地に旅行をするなどして,性交渉を伴った交際を続けていたのであって,その間,血酒の誓いや,伊勢神宮への特別参拝を経て,最終的には,共同経営をするに至ったのではあるが,それ以上に,原告において両親に被告との婚約を報告したり,被告においては既婚者であり原告と結婚するには法律上の障害があったにもかかわらず,夫と離婚の協議をしたりするなど,いずれも結婚に向けた具体的な行動をとった事実は認められず,このように,何ら外形的事実関係がないことに照らすと,両者間における婚約の成立については相当慎重に判断する必要があるとした。
そして,原告と被告の二人の間においてすら,結婚の時期や,結婚に向けた手続等について具体的な話が進んでいたとは認められないことからすれば,仮に,原告と被告間において,将来の結婚に関する言辞が交わされていたとしても,それは両者間における恋愛感情を高め,男女関係を維持するためのものとみるのが相当であり,これをもって法的保護に値する婚約とまで認めることはできないというべきであるとした。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月22日 21:52





連帯保証人の責任(H25.1.31判決)
当事務所では、不動産に関する案件も数多く取り扱っており、特に、賃料請求や立ち退きに関するご相談、連帯保証人の責任等に関するご相談も多いです。
そこで、今回は、連帯保証人に対して賃料請求がなされた事案に関する裁判例(大阪地判平成25年1月31日(平成24年(ワ)第6877号)建物明渡等請求事件)をご紹介します。
今回の裁判例は、事案の概要も裁判所の判断の内容もやや難しいので簡単に説明しておくと、貸主(家主)が、借主が賃料を払わないことを理由に賃貸借契約の解除をした後、連帯保証人に対して多額の滞納賃料の請求をした場合に、その請求が全て認められるかどうかという問題です。
これに対して、裁判所は、借主が行方不明となり、借主が賃料を払わないことが分かりきっているのに、家主が連帯保証人にこれを知らせず放置して、未払賃料額をふくれあがらせておいて、連帯保証人に対して全額を請求することは、貸主としての正当な権利の行使とはいえないとして、貸主の請求を一部しか認めませんでした。これは、連帯保証人の責任を制限した裁判例といえます。
(事案の概要)
本件は,建物賃貸借契約の賃貸人であるX(本件建物内に本店を置く会社)が,賃借人Aの連帯保証人であるYら(Aの連帯保証人である実兄Bの相続人3名(Bの配偶者及び子))に対し,賃貸借契約が賃料不払いを理由に解除されたとして,平成17年1月分以降の未払賃料の合計702万円及び毎月の未払賃料に対する年14.6パーセントの割合による各遅延損害金の合計約371万円,並びに,明渡済みまでの月額賃料の1.5倍の賃料又は損害金の連帯支払を求めた事案である。
XとAとの間の本件賃貸借契約には,賃貸期間を2年(ただし,賃貸人及び賃借人双方に異議がないとき又は一方から何ら申出がないときは同一条件で契約が更新される)とし,毎月の賃料につき支払を怠ったときは年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う,契約解除後退去済みまでは賃料の1.5倍の賠償金を支払うとの約定が存在していた。
(大阪地方裁判所の判断)
本件における争点は,Xの請求が信義則に反するといえるか否かである。
大阪地方裁判所は,本訴請求債権のうち,5年以上前の賃料債権については,時効により消滅したものと認められるとしたうえ,さらに,Xは,本件建物部分のある建物内に本店を置き,原告代表者も上記建物内に住所を置いており,Aによる本件建物部分の管理,賃料の支払等の賃借人としての義務の履行状況を容易に把握できる立場にあったのに対し,連帯保証人Bは,本件建物部分から離れた場所に居住しており,Aの賃借人としての義務の履行状況を十分に把握できる立場になかったこと,Aが荷物を残して行方不明となってしまうといった事態になり,本件建物の賃借人として負う債務の任意履行が全く期待できない状況に立ち至った場合にも,賃貸人であるXは,連帯保証人であるBを頼みとすることができる一方,Xが賃借人であるA不在の状況をそのまま放置して本件賃貸借が更新されるにまかせれば,それだけ連帯保証人であるBの負うべき負担はふくれ上がること,原告代表者がBに電話をしたのは,Aが行方不明となる前のことであって,しかも,Bに伝えた内容は全く判然としない上,Aが行方不明となった後は7年近くも何もせずに放置したことを原告自身が認めていること等に照らすと,平成16年9月にはAが行方不明となったというのであり,その賃借人としての債務の任意履行が全く期待できない状況が現出したといえるから,権利行使をするかどうかは権利者の自由であるとの原則を最大限考慮したとしても,少なくとも,本件賃貸借がAが行方不明となってから2回目の更新を迎えた平成19年5月13日以後に生じる関係については,XがBに対して連帯保証人の責任を追及することは信義誠実の原則に反し許されないというべきであるとし,Xの請求を棄却した。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月20日 22:30





契約社員の更新拒絶と慰謝料(H25.12.10判決)
最近,正社員と契約社員(有期労働契約社員)との格差などが問題となっていますが,今回は,雇用契約について、使用者による契約社員の契約更新拒絶が認められなかった裁判例(大分地判平成25年12月10日(平成24年(ワ)第557号正規労働者と同一の雇用契約上の地位確認等請求事件))についてご紹介いたします。
(事案の概要)
本件は,使用者であるY社(石油製品等の保管及び搬出入作業,貨物自動車運送作業等を目的とする株式会社)との間で有期労働契約を反復して更新してきた労働者であるX(Y社の支店で貨物自動車の運転手として勤務し,タンクローリーによる危険物等の配送を行っていた。)が,Y社が有期労働契約更新の申込みを拒絶したことは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,従前の有期労働契約と同一の労働条件での更新の申込みを承諾したものとみなされたと主張して,Y社に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め,更新拒絶期間中の賃金及び慰謝料等を請求した事案である。
(大分地方裁判所の判断)
本件の争点は,契約更新の合理的期待の有無及び更新拒絶の相当性の有無である。
裁判所(大分地裁)は,正社員と準社員(有期労働契約社員)との間には,転勤,出向の点において大きな差がないこと,正社員の運転手の配置の範囲が準社員のドライバーと異なるとはいえないと認定し,本件雇止め(更新拒絶)は,無期契約労働者(正社員)への解雇と社会通念上同視することができると判断し,Xの更新に対する期待には合理的な理由がある(労働契約法19条2号)と判断しました。
そして,Xの雇止めの理由としてY社が主張する事項については,そのような事実の存在は認められないとし,Y社の更新拒絶は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとは認められないと判断し,Y社は同一の労働条件でXによる更新の申込みを承諾したものとみなされ,Y社のXに対する賃金の一部及び慰謝料の支払いを認めた。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月20日 19:13





セクハラと慰謝料等(H22.6.15判決)
当事務所では、男女問題も労働問題も取り扱っていますが、その両方に関係するご相談として、セクハラに関するご相談も多いです。
そこで、今回は、セクハラ問題に関する裁判例(奈良地判平成22年6月15日(平成20年(ワ)第1020号)損害賠償請求事件(セクハラ)))をご紹介します。
セクハラ行為に対して、慰謝料などの損害賠償請求の一部が認められた事案です。
(事案の概要)
本件は,Y1会社に派遣労働者として雇用され,派遣先のY2会社の業務に従事していたXが,上司であった亡Aから,携帯電話の番号を聞かれたり,繰り返し性的な言動を聞かされたり,尻を触られるなどの本件セクハラ行為を受けたことから,抑うつ神経症を発症したとして,Y1に対しては不法行為に基づき,Y2については使用者責任に基づき,合計697万円余(ただし,Y1については,全損害の2割に相当する139万円余の限度で不真性連帯債務)の支払を請求した事案である。
(裁判所の判断)
本件の争点は,①セクハラ行為の有無,②セクハラ行為とXの抑うつ神経症との因果関係の有無,③派遣元Y1の不法行為責任の有無,④損害額等である。
裁判所は,争点①につき,亡Aは,Xに対して,携帯電話の番号を教えるよう執ように迫ったこと,Xに対して,背中の刺青を見せてほしいと言ったこと,「エッチしよう。」といった性的発言をしたり,作業中のXの尻を触ったりしたこと,Xに自己のメールアドレスを渡し,Xのメールアドレスを教えるよう言ったこと,Xに対して毎日のように業務と関係のないメールを送りつけたこと,亡Aは,Xからメールを送ることをやめるよう言われ,遅くとも平成20年5月30日には,Xのメールアドレスを削除した旨のメモを渡して,Xに対する一連の本件セクハラ行為をやめたこと,亡Aは,同年6月3日にはXに対して謝罪をしたこと,亡Aは,警察署での取調べにおいても,Xの携帯電話の番号を聞き出そうとしたり,尻を触ったことは認めたことが認められることからすれば,亡Aが,原告に対して,上記認定事実の限度で本件セクハラ行為を行ったことが認められるとした。
争点②については,Xは,同月4日までは,特段の問題もなく出勤し,健康上の理由で欠勤したことがないこと,Y2の安全衛生チェックシートの悪いという項目に丸を付けたことがないこと,亡Aから本件セクハラ行為を受けていた間も精神的な不調を訴えなかったこと,本件セクハラ行為について亡Aらと話し合った平成20年6月4日も健康上の問題が見られなかったこと,Xの夫Bが本件セクハラ行為についてY1との話合いに関与し始めてから原告の体調に変化が見られるようになったこと,Y1やCとの話合いはBが主導していたこと,亡Aが自殺した後も原告の症状が悪化したことが認められることから,本件セクハラ行為が原告の精神的な面に少なからず,影響を及ぼしたことはいえるとしても,抑うつ神経症の原因となったとまでは認められないとして,本件セクハラ行為と原告の抑うつ神経症との間に相当因果関係は認められないとした。
争点③について,派遣元会社は,派遣従業員との労働契約に付随する信義則上の義務として,派遣先において働きやすい労働環境を整備すべき義務があるものの,派遣元会社は,派遣先に対して,指揮命令権を有するわけではなく,派遣従業員も派遣先の指揮命令に服することになるから,派遣元会社としては,派遣先の経営方針に介入しない限度で派遣従業員の労働環境の維持に資する対応をとれば足りると解すべきであるとし,Y1は,派遣先企業であるY2に2名を派遣管理責任者として常駐させ,職場環境の見回りや従業員からの意見の受付などをしていたこと,意見箱を設置し,派遣従業員からの意見を聞く体制があったこと,安全衛生チェックシートで派遣従業員の心身の健康状態を把握していたこと,本件セクハラ行為が発覚するとX及びY1に事実確認を行ったこと,Y1に対して,Xの要望を伝えたこと等の事実によれば,Y2は,派遣元企業として,派遣従業員の心身の健康状態を把握し,意見を聞く体制を整えて,セクハラを未然に防止できる体制を築くとともに,本件セクハラ行為に対しても,適切な事後的措置をとったものと認められることから,Y2は,派遣元会社として,Y1の経営方針に介入しない限度で,派遣従業員に対するセクハラの対応策を講じており,上記労働契約上の信義則上の義務違反があったとはいえないとした。
争点④については,本件セクハラ行為と原告の抑うつ神経症との間に因果関係が認められないから,原告が抑うつ神経症を罹患したことによる治療費,通院にかかった交通費及び休業損害については,本件セクハラ行為によって生じた損害とはいえないとした。
慰謝料については,本件セクハラ行為の内容,本件セクハラ行為が約半年以上続いたこと等,諸般の事情にかんがみ,70万円が相当であるとした。このほか,弁護士費用相当額として7万円を認め,合計77万円が認められるとした。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月20日 19:07





養育費と子ども手当(H22.6.24判決)
当事務所には、佐世保では数少ない女性弁護士が在籍していることもあり、離婚や男女問題に関するご相談を受けることが多いです。
中でも、養育費や子ども手当に関するトラブルも多いので、今回は、養育費の算定と子ども手当の関係に関する裁判例(広島高判平成22年6月24日(平成21年(ネ)第569号)離婚等請求控訴事件)を取り上げます。
(事案の概要)
本件は,結婚して10年余りを経過し,3人の子どもをもうけた夫婦のうちの妻であるXが,夫であるYに対し,婚姻を継続し難い重大な事由があるとして,離婚(親権者をXに指定する旨の申立てを含む。)及び慰謝料300万円の支払を求めるとともに,子どもらの養育費,財産分与及び年金分割のための標準報酬等の按分割合に関する各処分を求めた事件である。
原審は,Xの上記各請求中,離婚(親権者をXに指定)及び慰謝料100万円の支払の限度で認容し,その余を棄却した上,YはXに対し,養育費として,子どもらが成人に達する日の属する月まで各月額7万7000円を支払うべきこと,財産分与として,760万円を支払うべきこと及び上記按分割合を0.5と定める旨の各処分をする旨の判決を言い渡したところ,Yが原判決を不服として控訴した。
Yは,控訴審において,養育費の算定に当たっては,平成22年4月1日から子ども手当が一人当たり毎月1万3000円支給されることになっており,また,来年度からはこれが増額されるため,同金額については,養育費から控除されるべきである旨を主張した。
(裁判所の判断)
本件の争点の一つは,養育費から子ども手当を控除すべきか否かである。
裁判所は,平成22年度における子ども手当の支給に関する法律は,次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために,平成22年度における子ども手当の支給をする趣旨で制定された同年度限りの法律であり,政府は,平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていること,その支給要件も,監護者である父又は母の所得に関する制限が設けられておらず,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の平成22年3月31日付け都道府県知事宛て通知においても,子ども手当については,子育てを未来への投資として,次代を担う子どもの育ちを個人や家族のみの問題とするのではなく,社会全体で応援するという観点から実施するものであると説明されていることからすると,子ども手当の支給は,民法上の扶養義務に淵源を有する養育費の支払に影響を与えるものではないと解されるし,少なくとも,平成22年度限りの法律である同法による子ども手当について,これを継続的な養育費算定において考慮することは妥当でないというべきであるとし,Yの主張を認めなかった。
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月20日 18:58





物損(車両の損害)(H24.3.15)
当事務所でご依頼の多い交通事故案件について,今回は,物損(損害賠償請求)に関する裁判例(東京地判平成24年3月15日(平成23年(レ)第1478号 損害賠償請求控訴事件)をご紹介いたします。
(事案の概要)
本件は,Yが運転する自動車とXが使用するタクシー車両(LPガス車,以下「本件車両」という。)との間で発生した交通事故により,本件車両が損傷を受け,損害を被ったとして,Xが,Yに対し,不法行為(民法709条)に基づき,本件車両の修理代金相当額及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。
Yは,LPガス車には中古車市場がないから,法定耐用年数(3年)を基準として定率法により減価償却して本件車両の時価額を算定すべきであるとし,本件車両は初年度登録から既に3年9か月を経過しており,修理代金は時価額を超え,経済的全損となると主張した。
原審は,経済的全損にはならないとして,Xの請求を全部認容したため,これを不服としてYが控訴した。
(東京地方裁判所の判断)
本件の争点は,本件車両の損害額である。
控訴審である裁判所(東京地裁)は,本件車両は,中古車市場が存在しないLPガスを使用し走行距離が約40万キロメートルに達するタクシー車両であるから,中古車市場が存在する同一車種,同一年式のガソリン車を使用する自家用車両の中古車価格を参考としても,その時価を合理的に認定することは困難であるとし,他方,自動車の時価が税法上の減価償却後の価格と一致するものでないこともまた明らかであって,法定耐用年数を基準として定率法により減価償却をしても,自動車の時価を適切に認定することはできないことから,本件については,タクシー車両の一般的な使用期間を基準として定率法により本件事故当時の本件車両の時価を算出し,これをもって本件車両の時価と認めるのが最も合理的であるというべきとした。
そして,タクシー車両の一般的な使用期間を5年,最終残価率を10パーセントとして,タクシーの時価を算出した上,再取得費用としてタクシーとしての装備に要する費用を加算した額が,修理費用を上回るから,経済的全損とはならないとして,修理費用相当額を損害と認定し,控訴人の控訴を棄却した。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月16日 22:36





脱法ハーブ(危険ドラッグ)と故意(H24.12.6判決)
弁護士といえば,弁護人としての活動を思い浮かべる方が多いと思います。実際には,弁護士が扱う事件全体の中では,刑事事件は少ないですが,当事務所でも,数多くの刑事事件を取り扱っています。
中でも,自動車運転に関する刑事事件は多いものの1つですので,今回は,危険運転致傷事件に関する裁判例をご紹介させていただきます。
また,最近,いわゆる脱法ハーブ(危険ドラッグ)が社会的に問題視されていることから,脱法ハーブ(危険ドラッグ)の影響による危険運転致傷事件に関する裁判例(京都地判平成24年12月6日(平成24年(わ)第817号危険運転致傷被告事件))をご紹介します。
(事案の概要)
本件は,被告人が運転開始前に使用した脱法ハーブの影響により,幻聴,幻覚又は意識消失等意識の変調を来し,前方注視及びハンドル・ブレーキ等の適切な運転が困難な状態で自動車を走行させ,その際の追突事故によって2名を負傷させたとして,危険運転致傷罪に問われた事案である。
弁護人は,被告人が,本件事故当時,正常な運転が困難な状態であることの認識がなかったことから,危険運転致傷罪の故意が認められず無罪である旨主張した。
(京都地方裁判所の判断について)
本件の争点は,被告人における危険運転致傷罪の故意の有無である。
京都地裁は,被告が平成20年冬頃からいわゆる脱法ハーブの吸引使用を開始し,使用後に自動車を運転した際,対向車線に大きくはみ出して走行したり,突如ブレーキをかけて停止することがあったこと等を認め,被告人は,運転を開始した段階で,脱法ハーブを使用することによって意識障害等を起こすことがあることを認識していたことは明らかであり,被告人が脱法ハーブ使用後に自動車を運転した際,その影響によって正常に運転ができなかったり,そのおそれが生じた経験が多数回あったことが認められること,妻と脱法ハーブによる事故に関するニュースについて会話した際には妻から脱法ハーブ等の使用の有無について追及を受け,事実に反してこれを否定する発言をしていたものである上,当時被告人は脱法ハーブを使用した上で自動車運転を繰り返しており,その際には「固まる」状態になったり,その間の記憶がないといった経験を繰り返していたものであるから,被告人は,脱法ハーブを使用し,その影響下で自動車を運転した場合,運転操作等が困難となって自動車事故を引き起こす危険性を一層強く認識したものと推認することができるとした。
そして,以上によれば,被告人は前記運転開始の時点において本件脱法ハーブをその直前に使用したことにより自動車の正常な運転が困難な状態となり得る蓋然性を認識していたといえることから,被告人に危険運転致傷罪の故意があったことが認められると結論づけた。
佐世保・長崎の弁護士
竹口・堀法律事務所
(竹口・堀法律事務所)
2014年10月16日 21:59